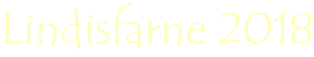
|
|
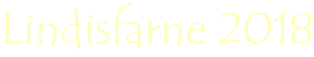
|
リンディスファーンはホリー・アイランドの名でも知られるイングランド有数の巡礼地。
毎年約65万人の巡礼者、観光客が訪れる。干潮時、砂浜がすがたをあらわし、人も馬も渉れるようになる。
リンディスファーン島は城以外に高い建物がなく、地平線も水平線もよく見える。島とブリテン本島を隔てるのは北海だ。
リンディスファーン島の舗装路は全長約5キロ、残りの道は地道である。
|
リンディスファーン島とブリテン島(本島)の距離は最も離れている地点でも4キロ強だ。
しかも干潮時は本島と地続きになって徒歩で行ける。
いま海の上にある舟も潮が引けば干潟の舟、その場に置きざりにされて身動きできない。
|
リンディスファーン修道院(後述)が廃墟となって時が経ち、1550年に建てられたリンディスファーン城は修道院の石が多用されたという。
1902−1910年、英国建築家エドウィン・ラッチェンス(1869−1944)によってリンディスファーン城は改装、一部拡張された。
エドウィン・ラッチェンスと女性造園家ガートルード・ジーキル(後述)の交流が知られている。36歳年上の造園家からラッチェンスは薫陶を受け、
彼女と中世の住宅や庭園を見て歩く。グレートディクスターのナサニエル・ロイド(と妻デイジーとの間に生まれたのがクリストファー・ロイド)との
交流もジーキルがいたからで、ジーキルの弟ハーバートとラッチェンスは1900年パリ万博の英国パビリオンの設計を共同でおこなった。
2018年8〜10月、英国映画「英国総督 最後の家」が上映されている。主人公のインド総督マウント・バッテン卿(1900−1979)が住んでいた
デリーのインド総督府邸宅(現在はインド大統領官邸)を設計したのもラッチェンスである。
インド総督府はラッチェンスの代表作であり、マウントバッテン卿夫人エドウィナをして、「バッキンガム宮殿より豪華ね」と言わしめた傑作。
|
木製の手すりは城の両サイドにあり、向かって左側の手すりからは村の中心部と城へつづく道、修道院跡などを見渡せる(後述)。
|
向かって右側の手すりから海岸と海が見渡せる。その向こうに見えるのは英国本島。左右の手すりからの眺望は全く異なる。
|
右側の手すり。何の木かは未調査。木の曲がり方をみれば針葉樹ではなく広葉樹。
異常気象、温暖化現象。だが北海からの風は冷たい。
|
生涯に何度「干潟の舟」を経験するだろう。身動きがとれなくなって困惑する。
若いうちなら満潮を待てばいい。老いて干潟の舟になると満潮はやって来ない。
|
城の高台からのぞむ景観は特に壮大でも優美でもないが、のどかなこと秀逸で、入江に沿って村から城へ続く道がよくわかる。
ガイドブックに紹介されない景色であっても、記憶に残る景色はある。
リンディスファーン島(ホリーアイランド)は東西最長約5キロ、南北最長約2.5キロなので、高台から島の全容を把握でき、
ウォーキングにも適している。島内に宿をとり、バンバラ城、ノーサンバーランド国立公園、逆方向のエディンバラへも楽に
日帰り可能(ノーサンバーランド国立公園まで約27キロ、エディンバラまで80キロ弱)。
リンディスファーンの2011年度統計の人口は180人。
|
村から城まで散歩する。観光客がほとんどいない時刻はいちだんと気分もよく、かといって道すがら誰にも会わない
というのもうら寂しい。
|
村にはバスの駐車場もある。だが貸切バスは城の敷地まで行って観光客を降ろし、
村の駐車場で待機し、時間がくれば再び城まで行って彼らを乗せる。時間の効率化ということだ。
村の駐車場からシャトルバスが出ている。が、利用するのは足に問題のある人だけのようだ。
ほとんどの人は歩く。駐車場から城まで2キロ弱、城は見えている。足が丈夫なら歩くほうがいい。
巡礼地なのだ。
|
車での訪問者は駐車場へ。村の環境保全に協力を。
|
歩き疲れた人も、そうでない人もコーヒーブレイク。
|
島ではボランティア男性が鷹匠ならぬメンフクロウ匠のミニ指導をおこなっている。
メンフクロウの顔はユーモラスであるが猛禽類、鋭い爪で野ネズミほかの獲物を捕獲。
わしづかみにされたら逃げ出す術はありません。叩いて払おうとすれば爪で引っかかれる。
|
リンディスファーン修道院、セント・メアリー教会は略図の左下にある。
|
向かって右がリンディスファーン修道院跡、左の小さな建物がセント・メアリー教会。見ての通り、教会は修道院の敷地に建てられている。
ノーサンブリアの王オズワルド(604前後ー642ごろ)の要請(キリスト教布教)によりアイルランド・アイオナ島の修道院から送られた
修道士エイダンが634年ごろ修道院を設立したという。後に聖人に列せられた聖エイダンの生没に関しては651年8月31日没ということだけで、
生年は590年ごろと推定されるにとどまる。
「当時まだ英語を話せなかったエイダンは、将来の布教のことを考え、英語が話せるフランシスコ修道会の少年見習い僧を12名連れてきた。」
と「イギリス・ヘリテッジ文化を歩く」(彩流社)に記されている。一説によるとオズワルド王がエイダンの通訳をしたともいわれる。
ある日オズワルド王の召使いが来て、貧しい群衆が慈悲を乞うていると言うと、王は自分の食べものを群衆に与え、さらに食べものを配らせた。
感動したエイダンは王の右手に「この手は滅びることのないように」と語ったという。
オズワルド王はノーサンブリアを8年間統治しキリスト教の普及をすすめたのち642年ごろ戦死するが、死後は聖人とみなされるようになった。
|
「Lindisfaren Priory」=リンディスファーン小修道院。村の南西部にある。Prioryは小修道院の意。
リンディスファーン修道院跡へのゲートは3月下旬〜9月末、午前10時から午後6時まで開いている。
ほかの時期は午後5時、または4時まで。
|
アーチが残っているだけでもさいわいと思うほかありません。いまにも崩れ落ちそうな
修道院の保全維持は手がかかるでしょう。
|
キリスト教の布教に尽力した聖エイダンの名はダラム大学の「セント・エイダン・カレッジ」として残っている。
北イングランド・ダラム州ダラム市にあるダラム大学は1832年設立と歴史は浅いが、ダラムは聖カスバート(後述)の遺骨を納める地として
995年に教会が建てられたことにより町がつくられ、1093年ダラム大聖堂(世界遺産)の建設以後発展する。大学の起源は大聖堂なのだ。
ダラムの名を冠したカレッジ創設についてはヘンリー8世治世の16世紀半ばにもあったが、オクスフォード大学の反対などで頓挫。
次に清教徒革命後の共和制時代、1657年には設立勅許状まで発行されたが、再びオクスフォード大の反対により腰くだけになった
オリバー・クロムウェルが大学に妥協し、計画は流れたという経緯がある。まったくもって権威というやつは。
|
リンディスファーン修道院跡のすぐ西にあるセント・メアリー(聖母マリア)教会。このグループも大学生。
50年前の京都奈良合宿を思い出した。
セント・メアリー教会は聖エイダンが修道院を創設したとき、修道院に隣接する場所に木造の
小さな建物二つ建てたという言い伝えがあり、
そのうちの西側の建物が改築を重ね、現在のセント・メアリー教会となっているといわれている。
修道院解散令によって修道院が閉鎖されたのち、セント・メアリー教会は教区教会として存続した。
現存の教会は16世紀以前の建築(外側)。
なお、墓石のなかで最も古い墓標は1686年のものである。
|
聖エイダンと聖カスバートを称える文章(聖蹟)。中央の修道士の画は聖カスバートだ。
|
セント・メアリー教会には「The Journey」という作品が置かれている。作者は彫刻家フェンウィック・ローソン(1932−)。
リンディスファーン修道院からダラムまで聖カスバートの遺骨を運ぶ6人の修道士。1999年の作品で、
最初はニューカッスル・アポン・タインで展示され、2005年セント・メアリー教会に移された。
ダラムのミレニアム・スクエアに展示の「The Journey」はブロンズ(2008年ローソン作)。
修道士6人の数字は、安息日以外の6日から人数が定まり、7日目の安息日は聖カスバートかもしれないと私は推測している。
聖カスバート(634ごろー687)は685〜686年にリンディスファーンの修道僧から修道院長になり、死後聖人に列せられたが、
カスバートの青少年期、聖エイダンの魂を天使が天国に運ぶ夢をみた。ちょうどその日(651年8月31日)の夜、
聖エイダンは亡くなったと伝えられている。
いつしか聖カスバートの遺物にふれると奇跡がおこるという噂が広がり、巡礼者がリンディスファーン島を訪れるようになったという。
|
793年ヴァイキングがリンディスファーンを襲撃し、修道院は荒れ果てる。その後もヴァイキングは略奪を続け、
875年、修道士らは聖カスバートの遺骨を携え北イングランドをさまよった。長年にわたる彷徨の
すえにたどりついたのがダラムの地である(聖カスバートの遺骨はダラム大聖堂に現在も安置)。
「ザ・ジャーニー」(旅)はニレの木。ニレの樹高は小さいものでも10メートル、大きいものは40メートル。
中米には80メートルのニレがあるとか。
|
リンディスファーン城から200メートルほどのところにガートルード・ジーキル(1843−1932)造園の庭がある。
園外からもみえるが、石垣越しに庭をみるより庭に入ってみるのがいい。城の眺めを計算して借景式庭園としたからだ。
この庭はガートルードが1906年から1912年にかけてデザインしたという。
石垣の小さな木製の扉に両手をおき、城を眺めている若い女性がいた。10分は見ていたろう。そして視線を落とし、
どこを見るともなく物思いにふけっていた。もはや城も景色も見ていない。ひたすら心の風景を眺めているのだ。
あるいは最初から城さえ見ておらず、過去を追想していたのだろうか。
|
ガートルード・ジーキルは造園家としてスタートしたわけでなく、その半生を画家・工芸家としてすごしている。
造園家となったのは眼病を患ったからだ。ガートルードは自然と自生植物を前面にだす作庭を提唱した。彼女の発想の
影響を受けた造園家は多く、そのなかに「グレートディクスター」のクリストファー・ロイドもいる。
ガートルードはコテージ・ガーデンと呼ばれる庭をつくりあげ、作庭に関して絵画の色彩法をとりいれた。四季の変化に
よって花も空気の色も変化するというテーマを庭づくりに応用し実践してゆく。この庭がイングリッシュ・ガーデンの原型
であることに異論をはさむ人は少ないだろう。
この庭はホワイトガーデンふう。白以外には目立つ色の花を植えていない。石垣越しの城が目に入っても落ち着いた
雰囲気をかもしだすためだ。
イングリッシュガーデンは枯山水のごとく思想が作庭に表現されるわけではない、作庭者の人生が表現されるのである。
|
ガートルードの庭はかつてリンディスファーン城の兵士のために食料を提供すべく耕された野菜畑だった。
彼女はその場所を庭に選んだのだ。
|
この部分はホワイトガーデンふうの庭と対照的。明るい色調の花が目にとまり、
視線を移せばシックな色合いの城があるという案配。
|
「Holy Island Causeway 」の名で知られる自動車道。ブリテン島(本島)とホリーアイランド(リンディスファーン島)を
2マイルで結んでいる。
一日2回の満潮時、道は消える。古代ブリテン島時代からリンディスファーン島を結ぶ最短道として干潮時に
利用されてきたという。
7世紀以降、巡礼者が往来。1950年代に舗装道路が建設され、島へ車で往き来できるようになった。
歩行者は別ルートを通る。別ルートはピルグリム・ウェイ(巡礼者の道)と呼ばれ、自動車道より長く約4キロ。
|
自動車道は駐車厳禁。完成後、道路の保全修理がおこなわれているというが、潮の満ち引きで道路が削られ、
すべりやすく急ブレーキをかけるとスリップする。
対向車との接触を避けるにはスピードを出さず、すぐ止まれるよう余裕をもって運転しなければならない。
時々大急ぎで走る車もいるが論外である。
|
リンディスファーン島と英国本島のコーズウェイはこの地点でつながっている。向こうは本島の道路だ。
引き潮のときはコーズウェイが設置されているのに気づかない旅行者(おおむね米国人)もいる。地続きにみえるのだ。
ここ(Beal)を西へ2.5キロ進めば英国の主要道A1と交差。この見張り台で監視している人を見かけたことがない、
|
潮が満ちてゆくに伴い車のスピードは緩やかになる。道路は満潮の2時間前と3時間後まで閉鎖される。
満潮時、道路は1.5〜4メートル海水の下になる。本島から島へわたる前、掲示板で安全な時間帯を確認せねばならない。
車の向こうに見えるのは本島である。
|
海水が押し寄せると車の速度はおおむね30キロ前後だ。それでも本島まで(2マイル)6分で着く。
徒歩なら別ルートを約4キロ、1時間ちょっと。
もうおわかりと思うけれど、向こうに見えるのは英国本島。中央やや上に小さく見えるのが見張り台(もどき)。
|
見取図左上部の赤い点線がホリーアイランド・コーズウェイと呼ばれる車道。
中央のやや長い赤点直線が干潮時の巡礼者道(The Pilgrim's Way)。
下のオレンジ枠は村の中心部、右下のキャッスルポイント近辺にリンディスファーン城がある。
|
歩いている人はみな裸足だ。6日間の滞在中、約4キロを徒歩で2往復した。長靴をはいた人は見なかった。
千数百年昔から現在まで長靴をはいて渉る人がいたかどうか知らないけれど、乾いていようが湿っていようが、
砂浜を素足で踏みしめてこその巡礼であるだろう。
|
満潮から干潮までの時間は約12時間25分だ。干潮の時間は毎日約50分づつ遅れてゆく。
満月や新月のころ、月、地球、太陽が一直線に並び、月の起潮力と太陽の起潮力が重なり合うため高低差の大きい「大潮」となる。
上弦(8日)、下弦(23日)のころには月、地球、太陽が直角に並び、月と太陽の起潮力が打ち消し合うため「小潮」となる。
2018年6月中旬〜下旬は6月20日が上弦の月だったが、その日は南仏リュベロン地方にいたので、イングランドに移動した
6月22日、つまり上弦の月の2日後はまだ「小潮」の日だった。
|
古代または中世、細い木の柱は巡礼者の道しるべだった。柱に沿って渉るのがいい。
1日2回、砂の道は満潮となり道は消える。柱の上部だけわずかに残っているのは危険のしるし。
|
巡礼者と観光客に向けて潮の干満状況はインターネットや巡礼者の道・出発点、村の掲示板に報告されている。
2018年6月22日〜28日の状況は、22日の干潮01:10−09:05、同日の干潮13:45−21:45、
23日の干潮02:10−10:10、同日14:50−22:45、24日の干潮03:15−11:10、同日15:50ー23:35。
27日の干潮06:10ー13:25、同日18:35−01:35、28日の干潮06:55ー14:00、同日19:15−02:10。
宇宙の営みはかなり正確なので、それを見て歩けばOKだ。
|
万が一の避難所だろう、確かめはしなかったけれど。遭難した人については救命艇などが救助に向かうのだろうか。
|
巡礼者は本島へ帰る。私は島の村へもどる。見知らぬ人に対しても寂寥感は残る。旅とはそういうものだ。
信仰とは何か。同じ方向をみて歩くことだ。そしてさまようことだ。魂のさまよう先につながりを見出すことだ。
つながりを見出しても魂の安息があるかどうか不明だ。しかし必ずいつの日か旅立ち、時は永遠に過ぎ去る。
|
あのときの風、風にゆれる雑草、スミレのような少女。時が経過して追懐する風景。
そのとき経験し記憶に刻まれたことは昔にも経験した。感動は永つづきしない。しかし感動はよみがえる。
あの日に帰るのである。
|
今回の旅で知った「セント・オズワルドの道」という名の道。
ノーサンバーランド州のステキな景色と魅力的な歴史を探索するルート。
ノーサンブリアのオズワルド王(7世紀 前述)に関連する場所を結びつけ、リンディスファーン島から本島にわたり、
北から南へ全長156キロを歩く行程はバンバラ(Bamburgh)城までの30キロ、バンバラ城からクラスター(Craster)
までの22キロなど6つのパートにわかれる。
終着点のヘヴンフィールドはオズワルド王がウェールズ軍と戦い勝利した場所で、セント・オズワルド教会
が建っている。
上の道は本島のB6353の東、バンバラ城へ向かう道路だ。巡礼を続ける旅人は歩きながら記憶をたどり、
過去の巡礼者と気持ちを共有するために歩くのだろうか。
|
| + | + |